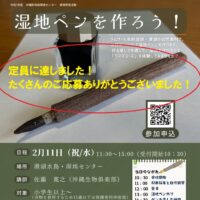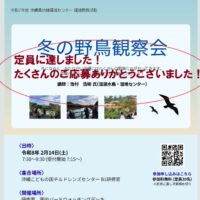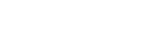県内には危険な毒ヘビ(ハブ)が生息するため、ヘビに対し過剰な恐怖心を抱いている県民の皆さんは多いと思われます。
しかし、実際、皆さんが日ごろ遭遇するヘビの約半数は無害なヘビです。
ハブの習性や対策法について正しい知識を身につければ、ハブに対する過剰な恐怖心を軽くすることができます。
■ハブ咬症注意報(令和年7年5月1日~6月30日)
本県には、猛毒を持つハブが生息し、年間60件弱の咬症被害が発生しています。
近年、ハブ咬症による死亡者はほとんどみられなくなりましたが、
未だ住宅敷地内でのハブの目撃・咬症事故が多く県民の日常生活に及ぼす影響は計り知れません。
ハブによる咬症被害は、私たちの注意によって未然に防止することができます。
県では、令和7年5月1日から6月30日までの間、ハブ咬症についての注意を喚起するとともに、
草刈り、餌となるネズミの駆除等の環境整備を呼びかけ、ハブによる被害を未然に防ぐよう広く県民に呼びかけます。
■ハブの習性
現在、県内に生息する毒ヘビで危険なものは、ハブ、ヒメハブ、サキシマハブ、タイワンハブの4種類です。
ハブは夜行性で日中は穴などに隠れています。
産卵は、初夏に穴の中で行われ、誕生した赤ちゃんは既に毒をもっています。
また、ハブは冬眠すると思われがちですが、ハブを含めた県内に生息する全てのヘビは冬眠しません。
■ハブを見かけたら・・・
1. 離れることが可能な場合は、1.5メートル以上距離を置きましょう。
(ハブはジャンプできません。1.5メートル以上離れていれば攻撃範囲外です)
2. 屋敷や畑等で見かけ、捕獲して欲しい場合は、各市町村のハブ対策担当課へ連絡し、捕獲してもらいましょう。
3. 身の危険を感じ、緊急で捕獲して欲しい場合は110番をし警察へ捕獲してもらいましょう。
■ハブに咬まれたら
1. まず、慌てずに、ハブかどうかを確かめます。
ヘビの種類が分からなくても、ハブなら牙のあとが普通2本(1本あるいは3、4本の時も)あり、数分で腫れてきてすごく痛みます。
2. 大声で助けを呼び、すぐに医療機関へ受診しましょう。
走ると毒の回りが早くなるので、車で病院に運んでもらうか、ゆっくり歩いて行くようにしましょう。
3. 病院まで時間がかかる場合は、包帯やネクタイなど、帯状の幅の広い布で、指が1本通る程度にゆるく縛ります。
血の流れを減らす程度にゆるく縛り、15分に1回はゆるめましょう。決して細いヒモなどで強く縛ってはいけません。
恐怖心から強く縛ると血流が止まり、逆効果になることもあります。
ハブに注意!(リーフレット)
ハブに関する普及啓発_A1ポスター多言語併記
沖縄県公式ホームページでは、ハブ抗毒素を常備する医療機関や被害発生状況など、
より詳しい情報が記載されていますので、併せてご確認ください。
ハブについて|沖縄県公式ホームページ